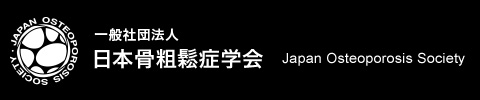ごあいさつ


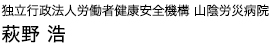
2024年12月
骨粗鬆症が原因の骨折(脆弱性骨折)の予防は超高齢社会のわが国の医療と社会保障における喫緊の課題として急速に浮上しています。特に、年間約22万件にも上る大腿骨近位部骨折は、2.4分に1件の割合で発生しており、これに伴う治療費用は医療費の重要な一部を占めています。脆弱性骨折は高齢者の生活の質を著しく低下させるばかりでなく、社会全体の経済負担も増大させています。このため、骨粗鬆症の予防と治療を通じて、脆弱性骨折のリスクを低減させることが急務となっています。
現在、わが国には推定1590万人の骨粗鬆症患者が存在し、これは国民の7.8人に1人という割合です。この疾患の予防と治療が、社会的にますます重要視されています。1990年以降、DXA(2重エネルギーX線吸収測定法)による迅速かつ正確な骨密度測定が普及し、骨密度と骨折リスクとの強い関連性が明らかにされ、骨粗鬆症の診断基準が確立されました。
近年、骨の役割が単なる支持組織にとどまらず、全身の健康に影響を与える重要な器官であることが広く認識されるようになりました。骨量の維持と骨の健康の改善は、脆弱性骨折の予防だけでなく、全身の健康に寄与します。2024年からの健康日本21(第三次)計画では、骨粗鬆症検診の受診率向上が重点項目に掲げられており、国民全体での取り組みが期待されています。
日本骨粗鬆症学会は1999年4月、初代理事長である森井浩世先生のもと、「骨粗鬆症に苦しむ人たちに対する治療と予防策の確立」を目標に設立されました。今年で25周年を迎え、現在は臨床医や基礎研究者をはじめ、看護師、薬剤師、療法士、栄養士、保健師、製薬会社など、多様な職種が参加し、会員数は1万1千人を超える規模に成長しています。2022年には骨粗鬆症リエゾンサービス(OLS®)に新たな診療報酬評価が加わり、当学会の取り組みが一層活発になりました。
本学会では、以下の活動を引き続き推進してまいります。
- 骨粗鬆症検診と早期診断の推進
- 二次性骨折予防の促進
- 運動や栄養改善による骨粗鬆症予防の推進
- 骨粗鬆症診断技術の向上
- 治療法の開発と普及
これからも最新の研究成果を基に、骨折予防と骨粗鬆症対策の普及を目指して邁進してまいります。引き続き、皆様のご協力とご支援を賜りますようお願い申し上げます。